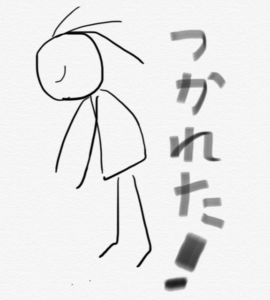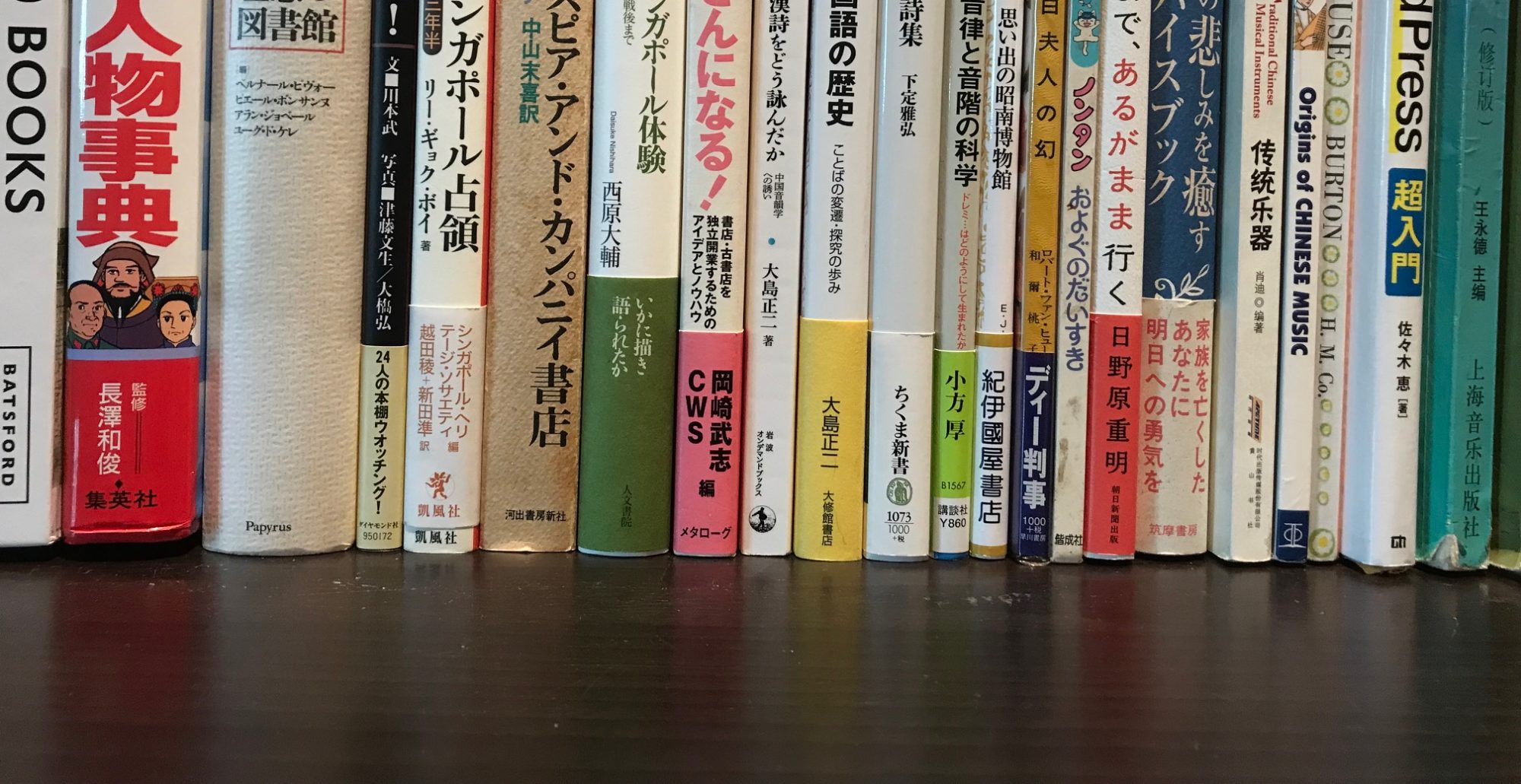久しぶりに折り紙動画を投稿した。視聴者数もチャンネル登録者数も減る一方だから、今一つモチベーションがあがらない。というより、「靴箱ミニチュアルーム」も12か月分作ったし、「ミニチュアハウス企画」もキッチンから始まって一応すべての部屋を作り終えたから、ドールハウスにこだわった折り紙はもうネタ切れ。新しいアイディアが浮かばないまま、古琴練習に没頭していた。
今回は「折り紙の歴史」についていろいろウェブで読んでいた時に発見した、非常に古い伝承折り紙「虚無僧」を作ってみた。例によって、無知な私だけが知らなかったのかもしれないが、この折り紙を見たのは初めてで、ちょっと感動した。
奴さんを半分に折っただけなので、折り紙の歴史上「奴さんより先」と言われると一瞬「ん?なぜ?」と思う。でも理由は簡単。本物の虚無僧が奴よりも先に出現していたから。奴という職業が出てきたのは江戸時代になってから。虚無僧はおそらく戦国時代、あるいはそれ以上前から「こもそう」などの名前で知られていたようだ、
私が子供の頃は、まだ街中で見かけるということがあったと思う(あ、江戸時代の話じゃないですよ! そこまで年輪は重ねていない。昭和、昭和!)。あと、テレビが普及するようになったら(初めは黒白だったけど……)、時代劇によく登場していた。怪しげな雰囲気で、悪者だったり、ヒーローだったり。でも、今、ふと考える。なぜ、あんなに顔がすっぽり隠れる編み笠をかぶっていたんだろう?
ウェブ情報の受け売りだが、初期の虚無僧は普通の三角形の編み笠で、着物は白、「こも」と呼ばれるゴザのようなものを腰に結び付けて行脚していたようだ。だから、折り紙の虚無僧の編み笠は初期のものを反映していると考えるとつじつまが合う。そのことからもこの折り紙の歴史の古さが感じられる。
虚無僧の着物の色とか持ち物とかが規制されるようになったのは、「不良」虚無僧が増えた江戸時代後期。明治になるとどんどんすたれていった。
……というわけで、いろいろおもしろいことがわかって(雑学だけれど!)、少し得した気分!
ネタ切れだけれど、折り紙も老化防止活動としては効果大だから、ぜひ続けたい! アイディアの神様、どうかお助けください!