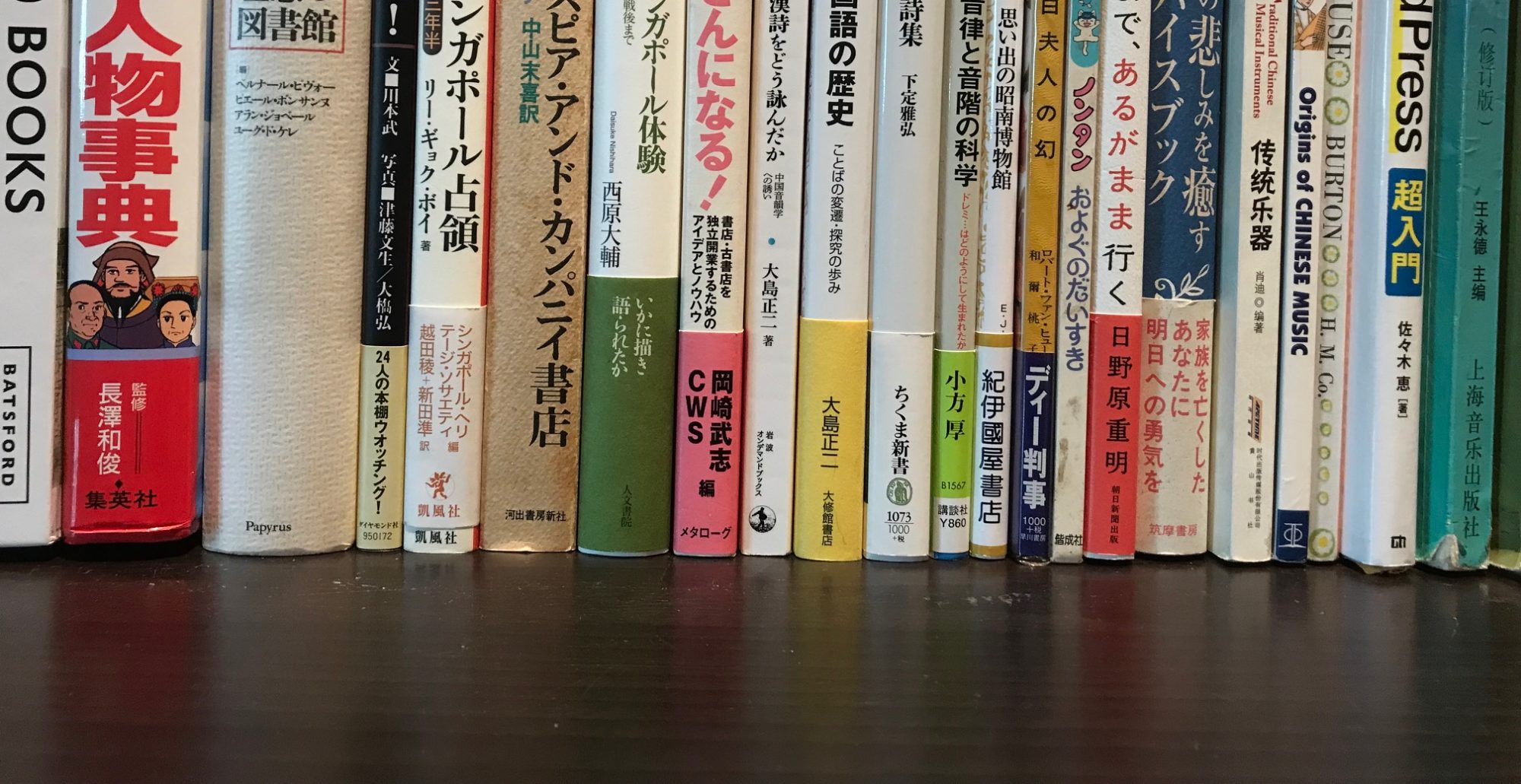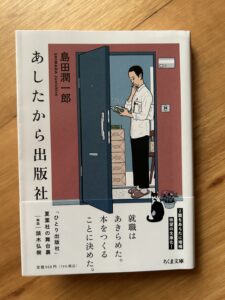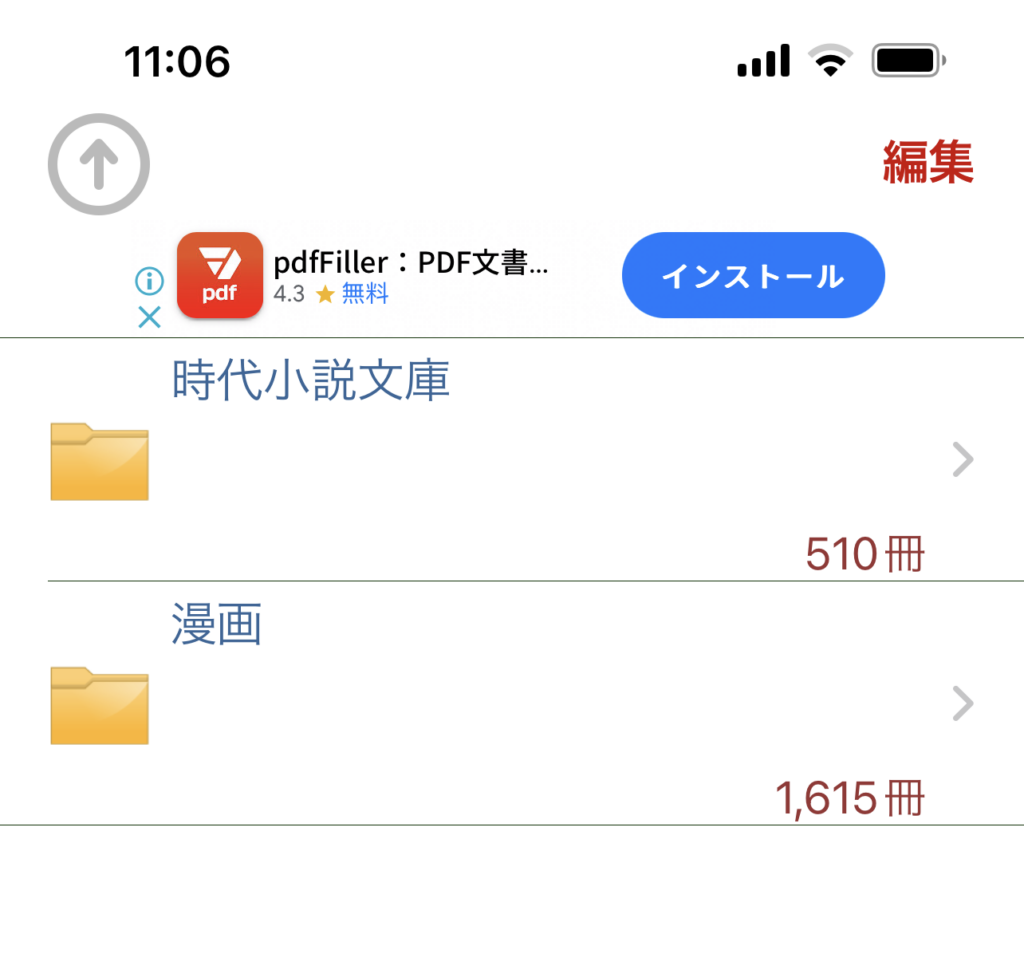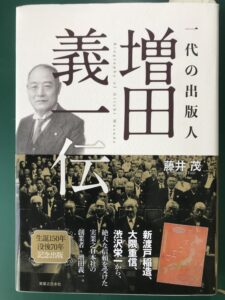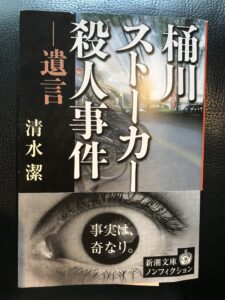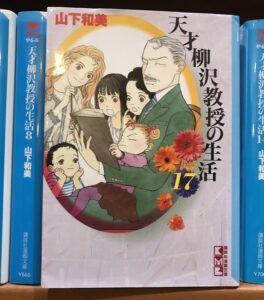昨日おもしろいことが起きた。どういう経過でそうなったのか、すでに記憶がさだかでないのだけれど、おそらく、子供の頃に読んだ本を思い出している時に、「例の絵本」を探してみようと思いたったのだろう。
例の絵本とは、今の天皇陛下のお父さん(上皇)についての本で、彼がエリザベス女王の戴冠式に参列した時の様子を描いた見開きのページが深く記憶に刻まれている本だ。
この本はこれまでも何度か「天皇」「昭和の絵本」などの言葉で検索していたが見つからなかった。
それもそのはず、絵本のタイトルが間違っていた。『皇太子さま』だったのだ! 昭和28年日本文化社発行。ネットにあがっていた中身の写真の中に、戴冠式の風景のページもあって、その構図はまさに記憶の中の絵と同じだった。ただ、記憶の中ではもう少し暗くて、荘厳な感じがしていた。幼い私が頭の中で作り上げた映像だったのだろう。
この本をもう一度手に取ってみたい!と思って探したら、ネットで2冊売っていた。最初に見つけた一冊は3万円近くして、「そこまではほしくないかな~」とか思っていたら、5分の一くらいの値段でもう一冊見つかった! 状態はあまりよくないみたいだけれど、あの見開きページをもう一度見られればそれでいい。
こういうのはタイミングだから、すぐに注文したほうがいいのだけれど、ここから注文すると送料が本よりも高くつくみたいで躊躇する。だから、ネットでよく買い物をする東京の友人に手に入れてもらえないか、頼んでみるつもり。