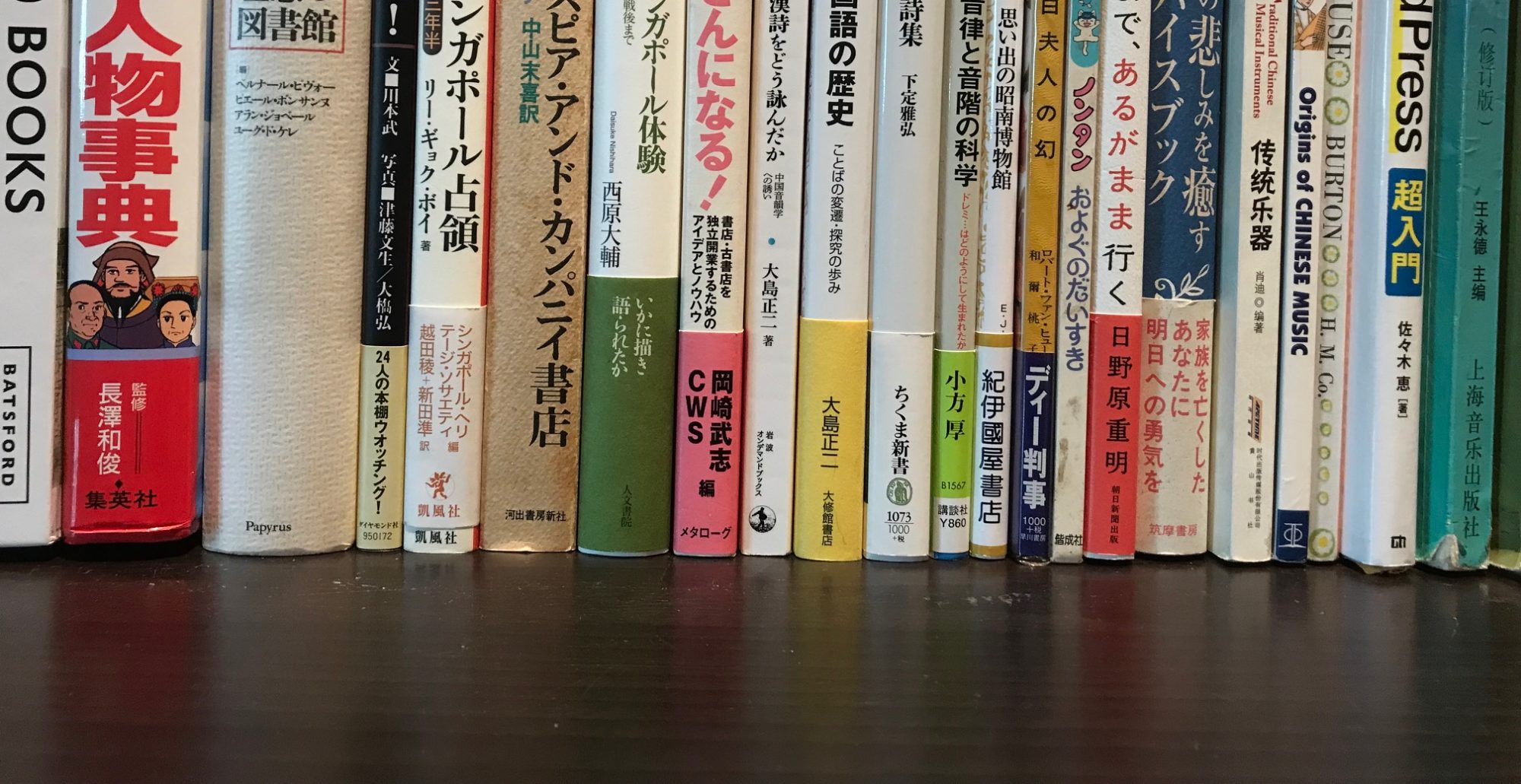ずっと前に見た、夏の湖の風景を描いた油絵の動画がとても印象的で、この間、秋のイチョウ並木の絵を描いたときに思い出して、「あれが描けたらいいな、でも、無理だろうな~」とぼんやりと考えた。
もとはかなり大きな絵だし、すごく緻密。それに、動画の撮影角度が絵に対して斜めなので、絵が実際より縦長になっているから、これを観ながら描くのはむずかしい……などの理由で、このアイディアは却下していた。
が、1月2日。「書き初め」ならぬ「描き初め」の日。「ままよ!」という掛け声も勇ましく(?)、6枚目のクレヨン画として、この絵に取り掛かってしまった。そして三日目。ギブアップ……。

やっぱり無理。今回はさすが恥ずかしくて、Kちゃんにも見せられない……。しかし、挑戦した意気込みは評価する!と、自分を慰める。
参考にしている油絵の動画は、まだ三分の一ほど残っている。これからどんどん緻密な細部が描きこまれていくのだが、クレヨンでは無理。
それに、そもそも、一番最初に描いた、遠くにある山と湖の色の選択を誤っているので、肝心なところが台無し。湖に見えない!!! 塗っているときに、なぜ気づかなかったのだろう?と、今になって思うけれど、謎のまま。たぶん、意気込んでいたから緊張したんだろう。「緊張しい」だからな。落ち着いて、よく考えて色を選ぶべきだった←今回の教訓①。
教訓②は油絵具とクレヨンの違いを考える。アイディアとしては、最初に全体に白を塗ることで、その上に重ねた濃い色を、場合によっては削ることができるようにする、とか、あとで削って出したい色を下地として塗る、とか考えられるけれど……そんなに前もって、色の配置なんて考えられないよお~!
教訓③。ある程度できたら、もうごちゃごちゃいじらない。お手本動画がいじっていても、(とくに画材が違ったら)もういじらない。色がきたなくなるばかりだから! それにいじり続けていたら、シングルタスクの私はほかに何もできない! 古琴の練習時間が少ないのも、中国語の学習時間が半減しているのも、掃除ができないのもそのせいじゃっ!
そこで、ひとまず、ここでやめることにした。クレヨン画の道具はうしろのソファの上に乗っけて、机の上を片付ける。よしっ、今日はほかの活動もやるぞっ!
(20220105)今朝、書斎のドアを開けたら、ソファの背に立てかけてあった絵が目に入った。数メートル離れたところから見たその絵は、なんか「それなり」に見えた。どうも、焦点を合わせずに見るといいらしい。もし、このブログを読んでくださる方があったら、上の写真はぜひ、眼を細めて「ぼんやり」させて見ていただきたい。生涯、図工コンプレックスを持ち続けている、当ウェブサイト管理人からのお願い……。
(20220108)結局、上の絵に少し手を入れて(地面に小さな花とかを咲かせて)、完成ということにした。楽しかった! これに懲りずにまた挑戦しよう。でも、次回(えっ、また描く気?)はもっと簡単なものにしようね。少なくともクレヨン画をお手本にするように!
(続報20220203)これまでに描いた6枚の絵を集めた「クレヨン画ギャラリー」を作りました。よかったらご覧ください。