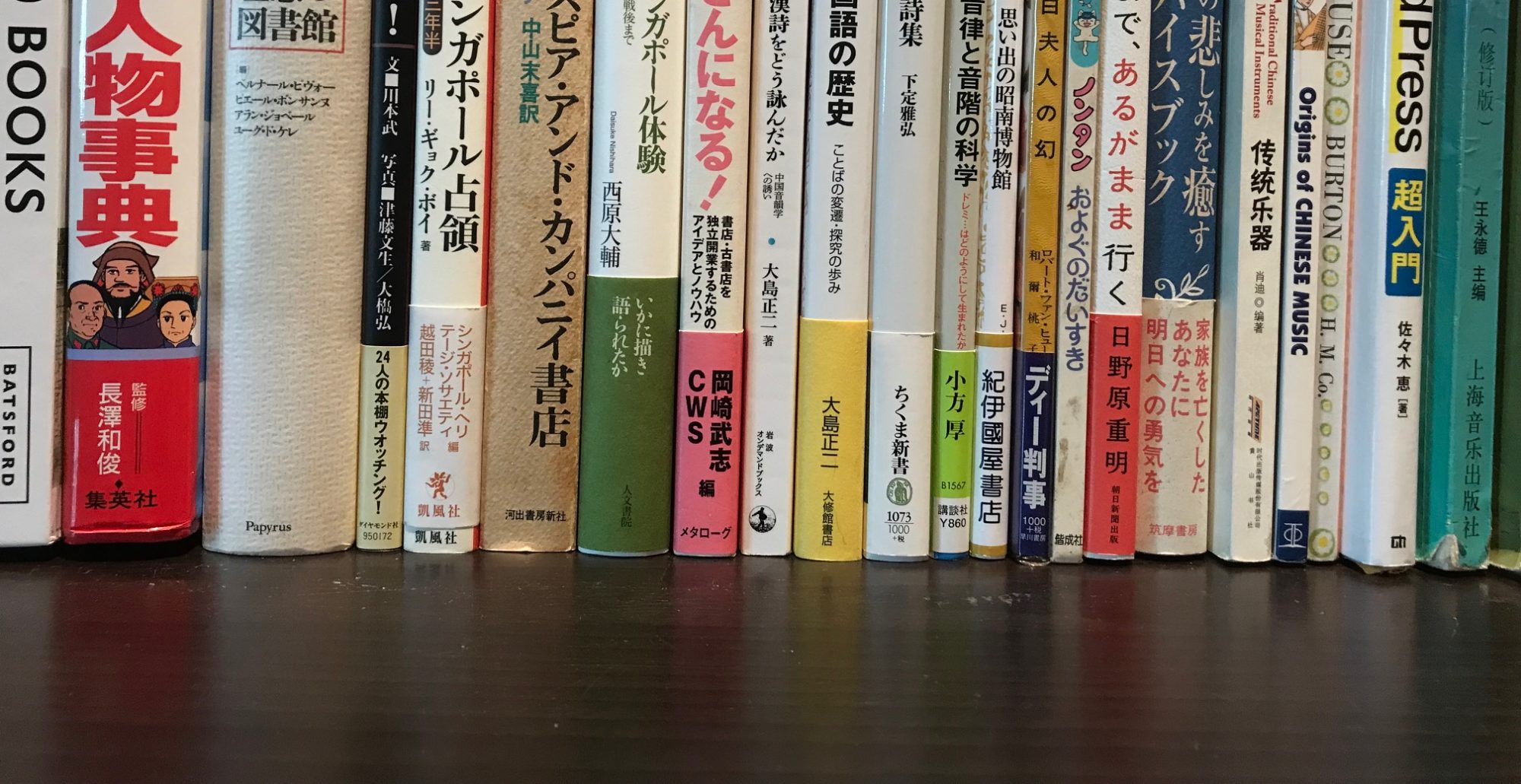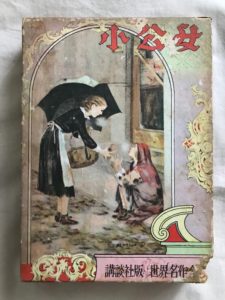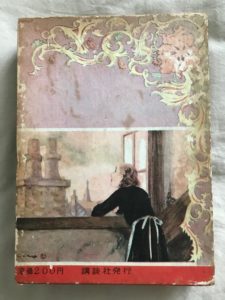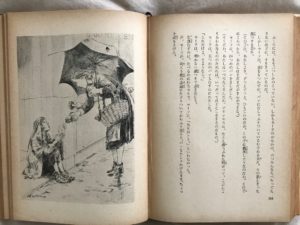備忘録:ブランドアカウントを作って動画を移動した後、iMovieで動画がアップできなくなった→アップする画面(「共有」ボタンを押す前)の下の方の「アカウント」をブランドアカウントに変える。
一昨日のブログに書いたように緊急措置で一本動画をあげたあと、「電脳技術顧問」の一人のKちゃんにもう一度これまでの状況、やってみたこと、などを説明した。そうしたら、なにか「ピン!」と来たらしく、iMovieに、「このアカウントに動画をあげますよ」と知らせるところがあるはずだ(KちゃんはiMovieは使っていない)、といろいろ探してくれたら、あった! 動画をアップロードするときの画面(左上に「共有」という選択のための文字が出ている画面)の「下の方」にアカウントを表示した行があった。それを新しいアカウントにしなければいけなかったらしい。
しかし、その場所は、スクロールしないと見られないのであった!
ほんの少しのスクロールではあるけれど、普通そこまで確認しないし、この動画アップ不能問題のさなかに、たとえ、ちらと見たことがあったとしても、そこにはもともとのメインのアカウントが示されていたわけだから、疑問はもたなくて当然(!?)だった。
ブランドアカウントを作ったら、ここを変えなければいけないということだったのだろうか? そんなことはどこにも書いていなかった。
そのうえ、今、チェックしてみたら、へ~んなアルファベット羅列が記載されていて、もしこれを別のアカウントにしなければならなくなったら、どうするんだい!? と思う。顧問が何をやったか、見ていたのだけれど、忘れた。もう一度聞きに行かなくては。(さらに下に「ログアウトする」という選択肢があるけれど、こわくて押せない。)
この数日、このことや、健康のことで作業や外出に時間が取られ、すっかり毎日の(午前中の)生活のリズムが崩れてしまった。中国語と古琴を練習するタイミングがまったくつかめない。昨日はとうとう古琴に一度もふれなかった。夜は時間があったのに! あ、爪がぼろぼろになっていたのだった。今から付け爪をつけて、練習する。練習したい。何もかも忘れたい。