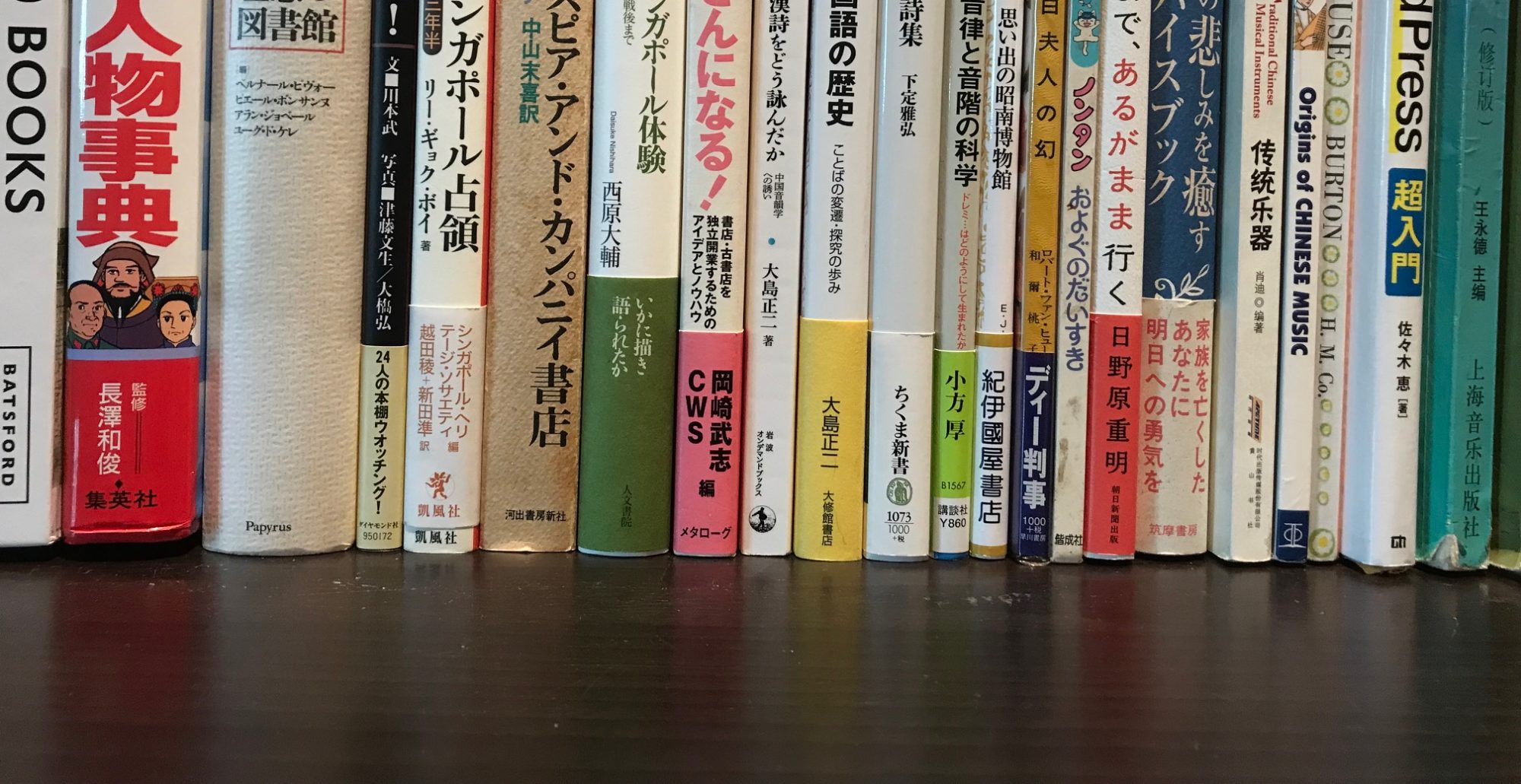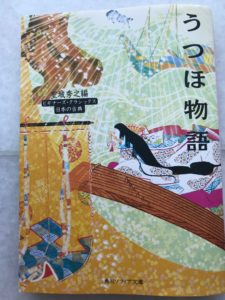「毎日聞き流しプロジェクト」まだ進行中。ただし、聞き流し時間は短縮されて、今日は40分くらい。というのは、「聞き流し」といっても、最近は、「聴き取れる単語を拾ってメモをしながら聴く、その単語が50個になったらやめる」というのをやっているので、その日によって違う。「表示」とか「报道」とか、頻出単語も数に入れているから、10個くらいはすぐ書けるけれど、そのあと、「何を言っているか全くわからない状態」で、単語を聴き取ろうとするのはかなり困難。(だから、「不过」「国家」といった基本単語も入れてしまう!)
というわけで、今日は40分。実は数日前に、ラジオを聴くのは「もうやめよう」と思った。時間の無駄、労力の無駄、と思った。それよりも、教科書のように「内容がわかっていて、文字であとで確認できるテキスト」を聴いたほうがよっぽど「効率がいいし、新出単語が覚えられる」と気が付いた。
6月初めに読んだウェブの記事では「三か月聴き続けると、聴き取れるようになる」と書いてあったけれど、それはある程度(3000語以上)語彙のある人の場合。「読んでもわからない文章を聴きとろうとすることの無意味さ、効果のなさ」がやっとわかった。
それでも、習慣になってしまったものはなかなかやめられなくて、そのうえ、生来の生真面目さが頭をのぞかせる。というわけで、3か月(90日)はやってみるか! という気持ちになっている。いずれにしても、もう半分は超えているのだから。今後は本当に「聞き流す」だけになる可能性は大いにあるが、何人かのアナウンサーの声には親しみを感じるようになっているし、「其他方面」とか「抗疫情况」とかたま~に聴き取れると感激することもあるので、もう少し続けてみる。3か月やってみて、「やはりこの方法は無理ですよ~」という結論が出ればそれでいいし。