古琴動画に続き、これまた久しぶりの折り紙動画投稿。
テレビのスタジオ再現シリーズで、私も時々観る『100分de名著』のスタジオの再現。コロナのために机が一人用になったり、出演者のあいだのスペースが広がったりと、最近スタジオの様子が変わった。
【注意】なぜか、上にリンク画面はリンクが効かないような表示になっていますが、かまわず再生ボタンを押すと再生します。それでもだめな場合はYouTubeの「小さな幸せ 折り紙 チャンネル」からどうぞ。
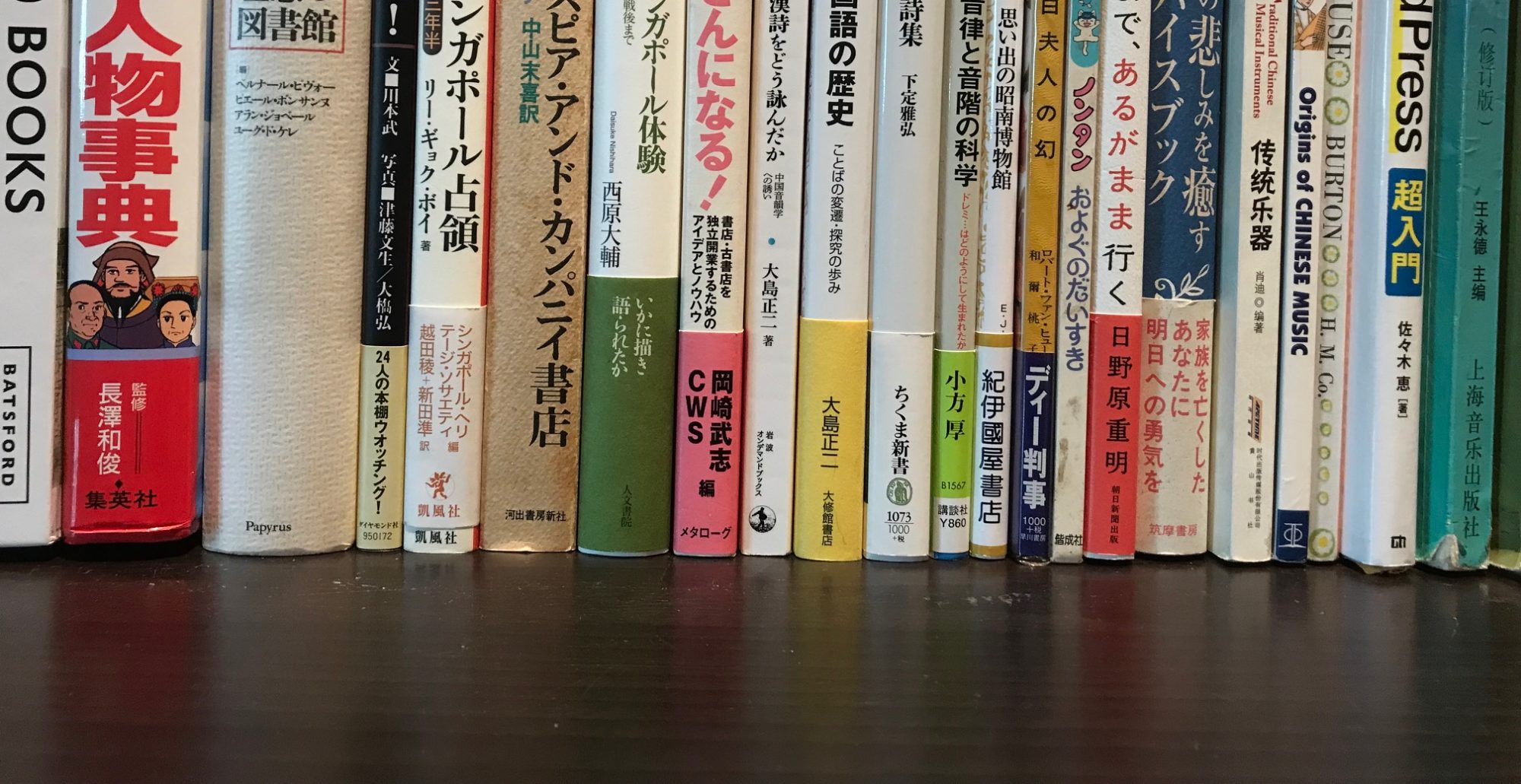
WITH GUQIN : 自分流で楽しむシンガポール生活 ――by 独坐弾琴
古琴動画に続き、これまた久しぶりの折り紙動画投稿。
テレビのスタジオ再現シリーズで、私も時々観る『100分de名著』のスタジオの再現。コロナのために机が一人用になったり、出演者のあいだのスペースが広がったりと、最近スタジオの様子が変わった。
【注意】なぜか、上にリンク画面はリンクが効かないような表示になっていますが、かまわず再生ボタンを押すと再生します。それでもだめな場合はYouTubeの「小さな幸せ 折り紙 チャンネル」からどうぞ。
何週間ぶりかわからないほど久しぶりの投稿。
10年前にはじめて古琴を手に入れたとき、すぐに練習を始めなかったことへの後悔。その時の自分に「がんばれ! ちょっと触ってみて!」と声をかけてみた。
この一か月間、古琴をほとんど弾かなかった。
正直なところ、弾いたのは5回。それも『广陵散』のみ(しかも楽譜を見ながら!)。前半、後半と分けて2日かけて弾いたのが2回。通してかろうじて一回。合計5回。合わせても2時間くらい……これほど弾かずにいたのは2016年にレッスンを再開してから初めてかもしれない💦
本当は東京でレッスンをとりたいと思っていた。でも、時間的にも精神的にもまったく余裕がなく、何とか倒れずに戻ってくるのが精いっぱいだった。
帰ってからも疲労がとれず、なかなか練習できないでいる。
三日かけて『广陵散』を分割復習。今日、やっと全曲通して弾いた。30分かかった。楽譜を見なければならなかったのは4か所くらいだったから、まあよしとしよう。すっかり忘れてしまったのではないかと、とても心配だったから。
ほかの曲は1か月以上、まったく弾いていないわけだから、どうなっているか……想像するだけで恐ろしい!

まあ、またぼちぼちと、ゆっくりと「独座弾琴生活」を再開しよう。
今回の旅行は崎陽軒のお弁当で始まり、崎陽軒のお弁当で終わった。
最初はおなじみシウマイ弁当。ハマスタに向かう途中、横浜駅で買った。横浜に来たらこれしかない!
東京滞在の最終日。幕ノ内弁当を探して新宿高島屋のデパ地下をうろうろしていたら、幕の内弁当と同じくらい好きな松花堂弁当を見つけた。しかも横浜の崎陽軒製、松茸ごはん! もうこれしかないでしょう! 成田のホテルの部屋で、一人でニヤニヤしながら日本の秋の味覚を楽しんだ。
今季は結局DeNAは2位で終わったけれど、Kちゃん曰く、これは「DeNA的にはほぼ優勝」。今日だって、巨人に勝ったんだよ!
セ・リーグの王者を決めるクライマックスシリーズというのは来週土曜日に始まるらしい。「I ♡ YOKOHAMA」のタオルを持って、応援するんだっ!
昨日、ベイスターズが負けて、ヤクルトの優勝が決定。「かつての地元」のよしみで、一応「優勝おめでとう」とは言っておこう。
しかし、ベイスターズが負けたのは無念。九回表まで0-0で、九回裏でのヤクルトのサヨナラ勝ち……。無念!
でも、残り試合もしっかり応援しよう。プロ野球にわかファンにはよく仕組みがわからないが、普通の試合(?)が全部終わった後、上位3チームで争うCSとかいうのがあるらしいし、そのあとパリーグのトップチームとの試合もあるみたいだから。

がんばれ、ベイスターズ。がんばれ、宮崎さん💛
雨での中断をはさんで4時間以上の試合。9回裏に5点も入れられて、7点差が2点差になってハラハラさせられた。結局勝ったから、「終わりよければすべてよし」ではあるのだけれど、最後にヤクルトに勢いをつけさせてしまったみたいで、明日が心配。どうか気持ちを入れ替えて、がんばってほしい!

「ベイスターズ応援しています」という気持ちを込めて、マスクに手製ベイスターズマークをつけた。にわかベイスターズファンだけれど、しっかり気合は入っている。
久しぶりに折り紙でミニチュアハウスを作った。チョコレート菓子『小枝』の箱の一部を使った1LDK。主に使ったのは3.75cm角の折り紙だから、折るのにだいぶ苦労したけれど、プレゼントした女の子の笑顔で報われた。

身内に不幸があったりして、ちょっとつらい毎日が続いているけれど、だれかを笑顔にすることができたのがうれしかった。
制作過程を動画にするのをすっかり忘れたのが残念! 動画が作れたら、それもプレゼントできたのに!
虫の知らせというのは、何かいやなことが起こる予感のようなものを感じることだと思っていたけれど、本当に虫が何かを知らせようとやってきたのではないかと思わされる経験した。
二日前、窓際に大きなカマキリを見つけた。花粉症がひどいから窓はずっと開けていない。それにここは3階。
体長10cm近い、結構大きなカマキリが隅っこでじっとしている。虫が特に苦手というわけではないけれど、ここまで大きいとちょっとこわい。

タオルでつかんで外に出そうと思ったけれど、タオルをかけたら、どこにいるかわからなくなり、つぶしてしまいそうでこわくてつかめず、結局いつものようにKちゃんにSOSを出して、ベランダに出してもらった。
そして、二日後の今日、義兄の訃報を聞いた。それで、あのカマキリはそのことを前もって教えに来てくれたのかな、とか、義兄が(すらりとした体形だった)カマキリに姿を変えてお別れに来てくれたのかな、などとちょっと思ったような次第。
『ムー』の読みすぎだとは思うけれど、ここ何十年見たこともないカマキリが家に入ってくるなんて、何か特別な意味があったとしても不思議はないように思える。
Y兄さま、どうかやすらかにお眠りください。
夢がかなった! 横浜スタジアムでのDeNAの試合の観戦! にわかファン3年目のハマスタデビュー! この写真を撮ったあと、疲労のため数時間寝たきり状態になってしまったけれど、それはそれでいい。いい冥途の土産ができた。

今日は幸せな朝ごはん。
いつもは温かいミルクにインスタントコーヒーを溶かしたコーヒーミルクだけの朝食なのだけれど、今日は特別。ルブラン(水戸にあるケーキ屋さん♪)の季節限定モンブラン付き!

一口食べてびっくり。口の中にさっと広がる甘さと風味。モンブラン好きの私は、先週はスーパーマーケットと駅前のケーキ屋さんで買って食べたけれど、やはり物足りない感じがすごくした。

今朝のはすごい! もったいなくて、半分はお昼ご飯のあとのデザートにとっておくことにした。大事なものはゆっくり、じっくり味わいたいタイプ……。
最近猛烈に忙しくて、つらいことも多いのだけれど、今日は、大好きな、特別な友達から贈られたモンブランに元気をもらって、がんばりたい。