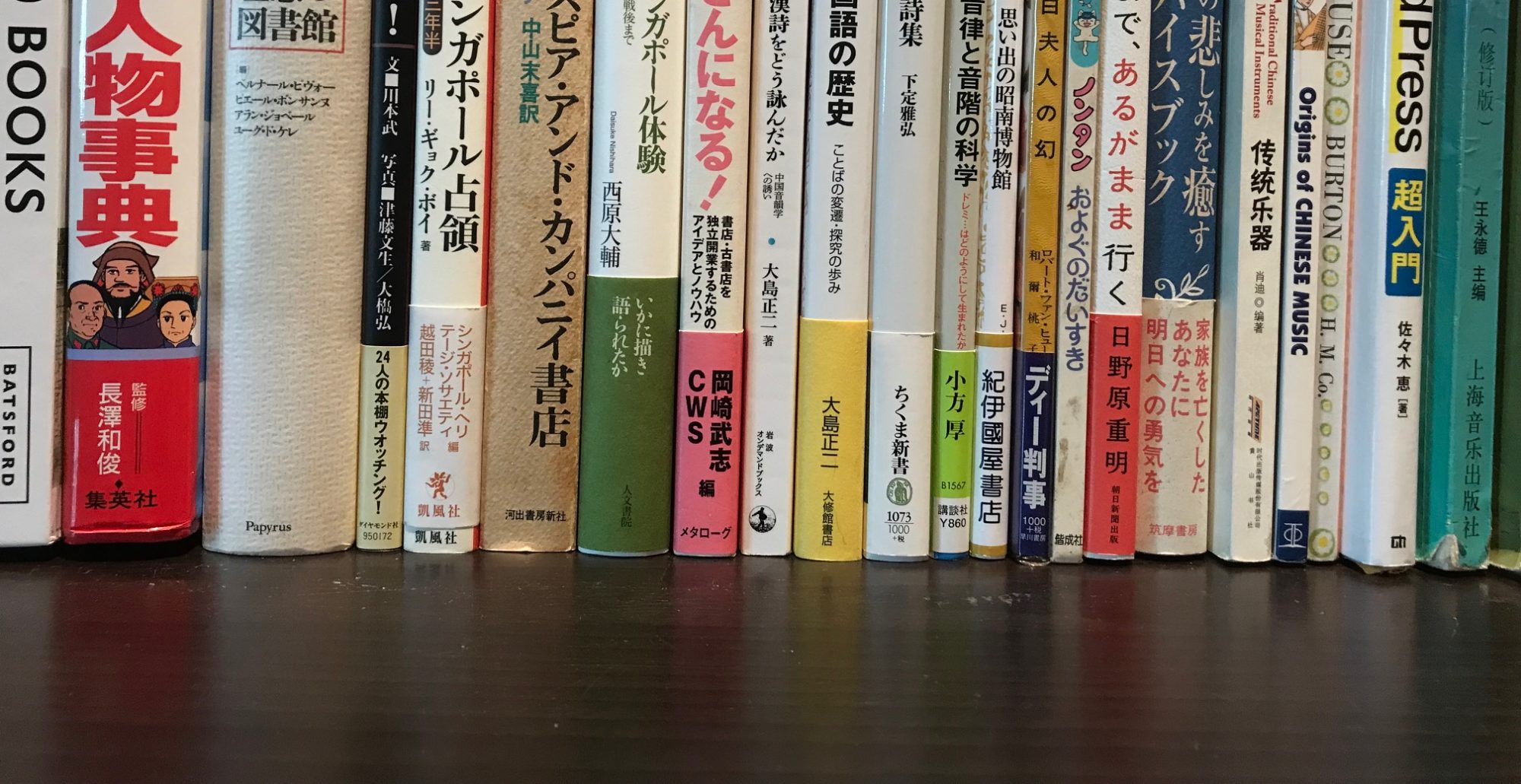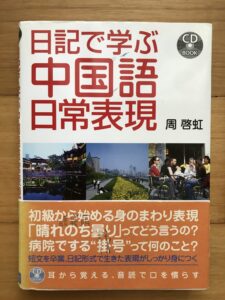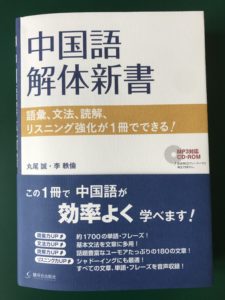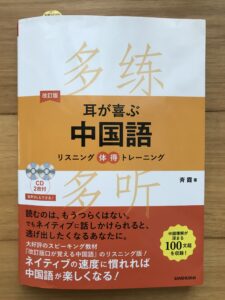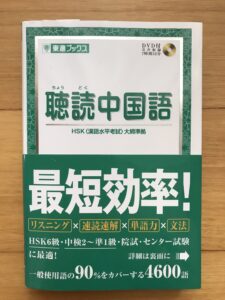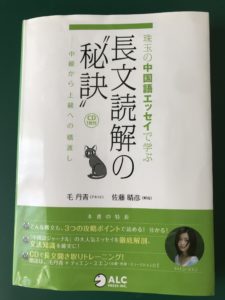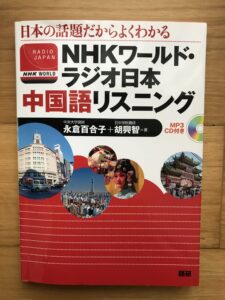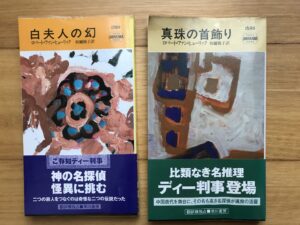【自分のための覚え書き】
数日前に「小さな幸せ 折り紙」チャンネルのチャンネル登録者が1000人に達した。それが達成出来たら、一つやりたいことがあった。それは、投稿動画から広告を外すこと。
今年(2021)のいつ頃からだったか、登録者1000人、一年間の視聴時間4000時間とかいう条件(広告収益化の条件)をクリアしていないチャンネルでも、YouTube側が「このチャンネルに広告つけたい」と思ったら、勝手につけていい仕組みになった。
その結果、私が投稿している動画にも広告がつくようになった。でも、月に何十万も稼ぐ人気チャンネルならともかく、ガチ素人、文系シニア女子が老後の楽しみ、ボケ防止活動の一環としてやっている動画に広告がついているというのは、どうも納得がいかなかった。
それで、調べてみたら、上記条件をクリアして、パートナープログラムというのに参加すると、広告からの収益を受け取ることができるが、それと同時に広告を無効にして、収益を受け取らないという選択もできるようになることがわかった。
で、やってみた。(やり方を覚え書きに残しておこうと思うのだが、途中経過は記憶だけが頼りなので、なんとも頼りない! PCの画面の写真を撮っておくのだった!)
①YouTube Studioの左側のメニューバーのようなところで収益化というのを選んでみると、1000人と4000時間という条件と、もう一つ、何かの規約違反で注意を受けたことがない……という感じの条件(よく覚えていない)の三つはクリアされていた。でも、4つ目の条件である「二段階認証の設定」というのはやっていなかった。そこでやってみたところ、珍しく、ウェブ上の指示に従うだけで簡単にできた! 必要なのは電話番号だけだった。これでパートナープログラム(以下PP)に申し込む権利が得られた。
②次に、収益化(PPへの参加)申し込み、みたいなボタン(だったと思う)を押したら、三つのステップでPPに参加できるらしかった。
一つ目のステップは、何かの書類(たぶんAdSense(以下AS)とかいうものについて、あるいはPP自体についてだったか?)を読んで、「同意する」こと。
③二つ目はASに申し込む(?)、というか、「ASのアカウントに関連付ける(?)」というか、何かそんな感じのステップ。怪しげなこと、意味がわからないことは決してやらない主義だけれど、YouTube, Google様は「信頼するしか選択肢なし」だから、これも「いいえ、既存のアカウントはありません」というのを選択したあと、ウェブ上の指示にひたすら従って申し込んで、「申し込み中」だったかPendingだったかの状態になった。
④三つ目のステップは二つ目のステップでASのアカウントができる(?)と、自動的にPPへの参加審査申し込みが始まると書いてあった。で、その審査が始まったあと、ウェブをいろいろ調べたら、承認されるまでにずいぶん待たされるとか、承認されないこともあるとか書いてあった。そもそも「審査プロセス始まりました」というお知らせの中にも「一か月くらいかかることがある」と書かれていたから、全然あてにしないで放って置いたら、なんと、一日くらいで「オッケー、あなたはPPに参加できましたよ」という知らせが来た。
⑤そこで早速、次の、動画広告を無効にするという段階にとりかかった。これもウェブを調べたら、YouTube Studioの「コンテンツ」から動画別に広告を「オン」にするか「オフ」にするかを選ぶという話だった。100個以上の動画に対して、一つずつ指定するのぉ?!と、がっくりしていたら、なんということはない、動画一覧を開けてみたら、すべての動画上でデフォルトが「オフ」になっていた。ラッキー♡
その後、以前に投稿した動画を一本観てみたけれど、少なくともそれには広告はついていなかった。ふむふむ、これですべての動画から広告が消えていればめでたしめでたし……なのか?? よくわからないままやっていることだから、本当にそうなったのか、まったく自信なし。時間のあるときに、またいくつか観てみよう。
まだ半信半疑のままだが、今日はもう遅くなったので、デジタル活動はこれでおしまい。