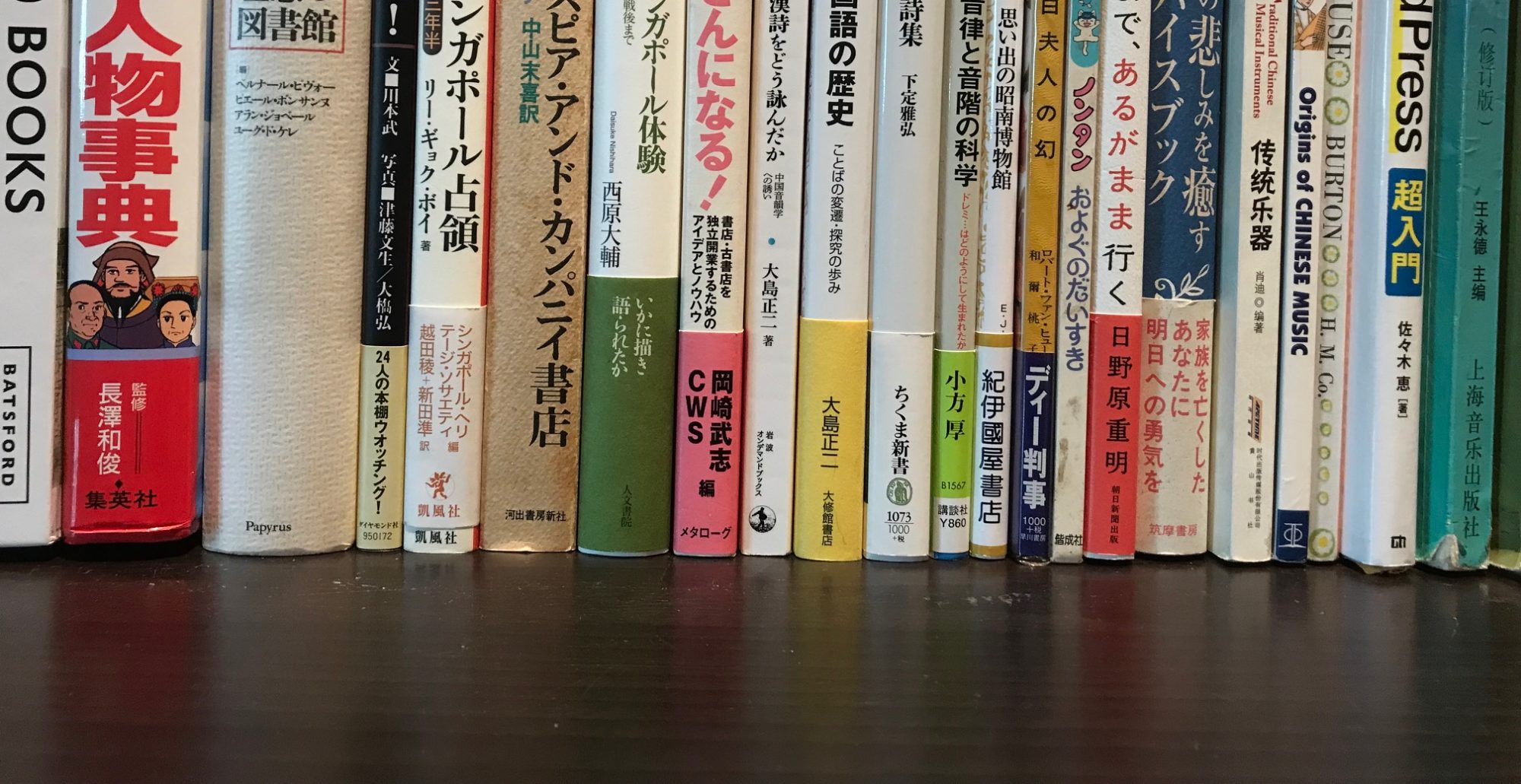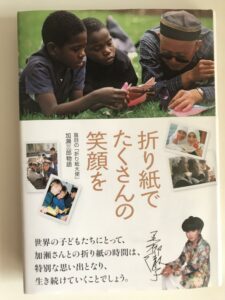古琴を始めたい、始めたばかりという方に勧めたい動画。
★他人の動画をブログ等にはめ込むことについては、ウェブ情報で「本来の作者を明記する。ただリンクを貼るだけでなく、独自の内容を加える」という二点がクリアされていれば問題ないことを確認しました。The copy right of these videos belong to the author of the videos and I am just adding explanation.
①4分でわかる古琴のこと 。シンガポールの楽器店、音楽学校のプロモーションビデオですが、日本語の字幕がしっかりついていて、先生の誠実な話し方が気にiいっています。超入門。
VIDEO
②日本語で古琴入門 。日本古琴振興会の武井先生による動画。先生の書かれた教則本はおそらく唯一の日本語古琴教則本。このレッスンが第一回しかないのが残念! 先生、続きの動画を待っています!
VIDEO
③当ウェブサイト管理人が古琴を始めた時、よく観た一無弦堂の李程 さんの動画。中国語が未熟で、ほとんど聞き取れないが、字幕がついているのでだいたいの意味はわかる。黒板を使った説明が、学校のようで楽しい。古琴を独学で始めようと思っている人にぜひお勧め したい。The teacher is Li Cheng (李程)from Wu Xian Tang (無弦堂)whose explanation and demonstration in these videos, I think, are really helpful to Guqin beginners.
ただ、現在YouTubeにアップされていて、ここでリンクできるのは下記、1、2、8課のみです。bilibiliという中国の動画サイトには全部あるようですが、リンクができません。興味がおありの方は検索してみてください。
1.ゼロから始める古琴(一)Start Guqin from scratch (1)
VIDEO
2.ゼロから始める古琴(二)Start Guqin from scratch (2)
VIDEO
3.ゼロから始める古琴(三)Start Guqin from scratch (3)
4.ゼロから始める古琴(四)Start Guqin from scratch (4)
5.ゼロから始める古琴(五)Start Guqin from scratch (5)
6.ゼロから始める古琴(六)Start Guqin from scratch (6)
7.ゼロから始める古琴(七)Start Guqin from scratch (7)
8. ゼロから始める古琴(八)Start Guqin from scratch (8)
VIDEO
9.ゼロから始める古琴(九)Start Guqin from scratch (9)
10.ゼロから始める古琴(十)Start Guqin from scratch (10)
11. ゼロから始める古琴(十一)Start Guqin from scratch (11)
12. ゼロから始める古琴(十二)Start Guqin from scratch (12)
13. ゼロから始める古琴(入門曲)《仙翁操》Start Guqin from scratch (Xian weng cao)
④上記と同じチャンネル(lokyee 90)に集められている真朴书院の初級レッスン動画 。これも中国語ですが、いろいろな角度から手元を写しているので、言葉がわからなくても大丈夫。「悪い弾き方例」をやってみせたときには画面に×印が出るのがありがたい。
VIDEO
上記動画は第一回目のレッスンです。全部で20課以上あります。基礎が終わったところで習う練習曲がドラマ三国志演義の主題曲らしくて(中国語で説明されているので、今一つ確信がありません)、古典曲と違って新鮮。
コメントを読むと、このシリーズで古琴を独学している方もたくさんいらっしゃるようです。
③よく使われる『古琴実用教程』という教則本の著者、李老师の動画 です。これも中国語ですが、字幕がついているので理解の助けになります。
VIDEO
④