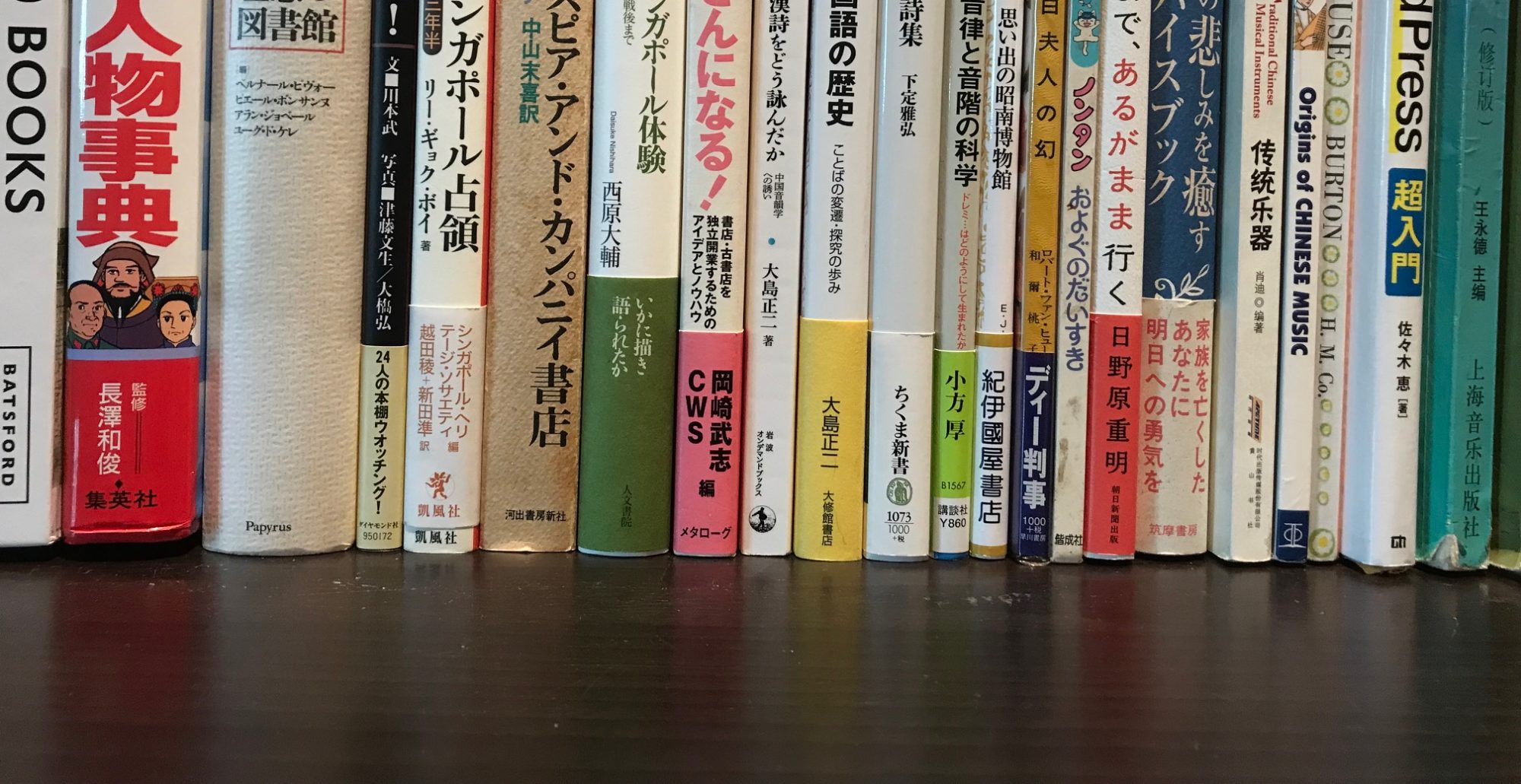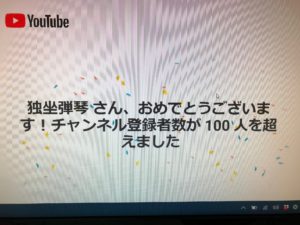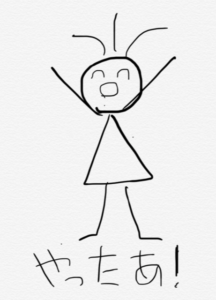4月と言えば新入学の季節! 今年(2020年)はコロナウイルスの影響で気持ちが沈んでいるけれど、なんとか日常が取り戻せるように祈りつつ、双子の新一年生の子供部屋を作りました。まだ部屋の紹介動画をご覧になっていない方はまずこちらからどうぞ。
VIDEO
家具や小物はこれまで作ったミニチュアハウスやミニチュアルームからの借用が多いのですが、このブログで、できるだけ多くのアイテムの作り方動画を紹介したいと思います。
【お断り】目次で利用する「ページ内ジャンプ」がまだ(!)できません……どうやら今使用しているWordPressのテンプレートでは、どうしても行(ぎょう)がずれてしまうようです。ウェブ初心者の管理人にはその調整ができません。読みたいところまで、スクロールお願いします……。
目次
①ランドセル School bag
VIDEO
②小学生の帽子 School hat
VIDEO
突然ですが、ここでクイズです。下の写真と、このブログの先頭の動画サムネイルとで、違っている場所が一か所あります。それはどこでしょう? 5秒以内にお答えください!!(答えは写真の下)
正解は、「帽子」です! サムネイルでは黄色い帽子が二つとも女の子用の丸い帽子になっていますが、この写真では一つが男の子用の野球帽タイプになっています。よ~く観るとわかっていただけるかと思います……だめかな……。
実は、当ウェブ管理人が子供のころ、あるいは管理人の子供が小学生だったころは、男女とも、丸い帽子だったのです。それで、男の子と女の子の双子の部屋、という想定で作った部屋に同じ帽子を二つ置いたのです。
ところが、つい最近ふとしたきっかけで、今は男の子と女の子で異なるのだということを知りました。それで、すぐに動画の説明を「双子の姉妹」と書き直した(動画を撮り直す体力・気力はないのです……)のですが、やはり最初の設定どおり、男の子の帽子も置いてみたいな、と思って作りました。作り方は下の動画を参照しましたが、正直に言ってミニチュアサイズで作るのは「かなり」厳しかったです。でもこれもかわいい!
VIDEO
実はこれより簡単な野球帽の作り方もあります(検索するとすぐ出てきます)。ただ、このミニチュアルームでは、「糊を使わずに、ランドセルラックの後ろの壁に掛かっているように見せることができる」、という点にこだわったので、この作り方にしました。
③本立て付き学習机 Desk with book stand
VIDEO
よくある、学習机の前面に合体された二段の本立てはどうしても再現できず、一段だけの本立てとなりました(20210420二段の本立ての作り方、下に追加しました!)。電気スタンドは超ミニ。
VIDEO
(続報20210420)去年10月のミニチュアルーム制作の際に、二段の本棚を作ることに成功しました!
VIDEO
本はミニチュアハウスの作り方でも紹介した作り方で作っています。ただし、四分の一の大きさの折り紙で作るので、結構大変です!
VIDEO
④整理棚(ランドセルラック) Storage rack
VIDEO
⑤ピアノ Piano
VIDEO
折り紙ミニチュアルーム企画も4月までたどり着きました。いつまで続けられるかわかりませんが、いつもの「乗りかかった舟だ」方式で、なんとかがんばりたいと思います。
ブログに♡マークがついたり、動画のチャンネル登録者が増えたりすると、とても励みになるので、ワンクリックで「おもしろかったよ」とお知らせくださるとうれしいです!
やっとほぼ全部のアイテムの作り方の動画が用意できました。最後のほうは息が切れてしまって、編集時間が非常にかかる字幕を少なくするように動画を撮ったりしたので、ちょっとだらだらした動画になってしまいました。わかりやすい、見やすい、すっきりした動画をあげている人たちは一体どんなふうにしているのだろう……と思う毎日です。でも、私は私。iPhoneとiMovieだけで文系シニア女子がどこまでできるのか、挑戦のつもりで素人動画アップを続けていきます!
おもしろかったと思われた方、これをみて自分でもやってみたくなったという方は、♡マークでお知らせください。自分でブログを始めるまでまったく気が付かなかったのですが、というかむしろ「いいね!」ボタンのたぐいは好きではなかったのですが、ブログ作者にとってこれが大きな励みとなることに、遅ればせながら気づきました。いつも応援してくれている方々、ありがとうございます!